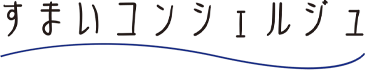お茶の水駅前にある、ある店舗物件が気になって仕方ありません。なぜかって?それは「お店がコロコロ変わる店舗物件」として、ちょっとした話題になっているからです。駅前という立地にもかかわらず、次々とテナントが変わるその場所。興味が湧いて、少し調べてみることにしました。
最初に耳にしたのは、「あそこ、昔は五右衛門だったよね?」という話。そう、あの有名なパスタチェーン「洋麺屋五右衛門」です。でも、よくよく思い出してみると、五右衛門の看板って、実はちょっと見づらかった記憶が…。いや、正確に言うと、五右衛門の看板の左下あたりに何か別の看板が重なっていて、全体がちゃんと見えなかったんですよね。気になって現地をチェックしてみると、今はその場所、鰻屋さんになっているらしいことが判明しました。しかも驚くことに、その鰻屋さんも近々閉店するとの噂が流れているとか。え、駅前なのに? 人通りも多いはずなのに? 何が起きているんだろう…と、ますます好奇心が湧いてきました。
お茶の水駅といえば、学生街としても知られ、オフィスも多いエリア。昼夜問わず人が行き交う、まさに一等地です。そんな場所にある店舗物件が、なぜか安定しない。新しいお店が入ってはみるものの、すぐに別のテナントに変わってしまう。この現象、ただの偶然じゃない気がします。そこで、ちょっと視点を変えて考えてみることにしました。立地が良いだけではダメなのかもしれない。もしかして、鍵を握るのは「視認性」なんじゃないか、と。
そう、五右衛門の看板がちゃんと見えなかったこと。あれって実は、この店舗物件の運命を暗示していたのかもしれません。駅前で人通りが多いとはいえ、通行人にお店の存在をしっかりアピールできなければ、集客にはつながらないですよね。鰻屋さんも、もしかしたら同じ問題に直面しているのかも。看板が目立たない、店舗の入り口が分かりづらい、なんてことが続くと、いくら美味しい料理を提供していても、お客さんが入りにくい状況になってしまう。実際、街を歩いていて、「あれ、ここにお店あったんだ!」と後から気づくことってありますよね。そういう小さな見落としが、実はお店の命運を左右する大きな要因になっているのかもしれません。
視認性の重要性って、普段あまり意識しないけれど、こうやって具体的な例を見ると、改めてその影響力に気づかされます。お茶の水駅前のこの物件、立地は抜群なのに、視認性がネックになってテナントが定着しないとしたら、ちょっともったいない話です。次にどんなお店が入るのか分かりませんが、もし私がオーナーだったら、まず看板の位置やデザインを見直して、道行く人に「ここに美味しいお店があるよ!」と一目で分かるようにするかな。だって、せっかくの一等地なんだから、そのポテンシャルを最大限に活かしたいじゃないですか。
この「お店がコロコロ変わる店舗物件」の謎を追いかけていると、不動産や店舗経営の奥深さにも気づかされます。立地、視認性、内装、サービス…いろんな要素が絡み合って、お店の成功が決まる。お茶の水駅前のこの場所が、いつか「ずっと愛されるお店」で埋まる日が来るのか。それとも、また新しいテナントが短命に終わるのか。ちょっとしたミステリーみたいで、今後も目が離せません。次に通りかかったときには、また新しい発見があるかもしれない。そんな期待を胸に、今日もお茶の水の街を歩いてみようと思います。